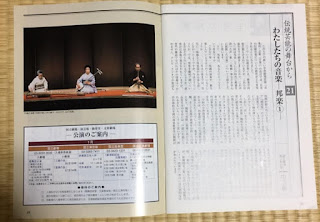…そういうわけで、僕も「ミュージシャン」のはしくれですので、常に尺八(二つ折りすれば、カバンに簡単に入る)、つゆきり、そして三浦琴童譜(琴古流の原点である、尺八本曲が全て記録されている)は、仕事に行くにも私用で出かけるにも、必ずカバンに入れているわけです(例外として、修学旅行、林間学校など、職務上いざという時は荷物をかなぐり捨てなければならないかもしれないときだけは、家に置いていきます)。
さて、何の話か分からなくなってきたのですが…、…そうそう、で、その「三浦琴童譜」を持ち歩いていると、周りとぶつかったり、ひどい雨の時は浸み込んだりするかもしれないということで、100均で購入したA4サイズのチャック付きケースに入れています。
これは非常に優れもので、ビニールで出来ているのでそんなに簡単には水を通さないのと、結構分厚いので本の保護もしてくれます。さらに、三浦琴童譜を入れた状態で縦に二つ折りできるため、背中に背負うような細長いカバンにも、二つ折りした吹料とともにすっぽり入ってしまうのです。
ところが最近、数年の使用の結果、だいぶこのケースが痛んできましたので、100均の有名店「ダイ⚪︎ー」に新しいのを買いに行きました。しかし…、以前ちょうどよかったサイズよりもなぜかどれも小さく、「ピッタリA4サイズ」という感じで、三浦琴童譜2冊を入れるとピッタリすぎて「二つ折り」になってくれないという問題が発生してしまいました。
仕方がないので、様々な「ダ⚪︎ソー」の店舗を周りましたが、どの店舗でも「ピッタリA4サイズ」ばかりで、ちょうどいいのがありませんでした。
諦めかけていたところ、本日たまたま、「⚪︎イソー」さんとは違う「Can★Do」という100均を発見し、チャック付きケースの売り場を確認したところ、なんと以前の通りすこしゆとりのある、理想通りのサイズのA4版のケースが「クリア・ポーチ」の商品名で売ってありました。
直ちに購入し、早速三浦琴童譜を入れてみたところ、これまで通りいい感じに入りました。一安心でした。
※ダイソ⚪︎さんの現行商品とは、これだけ大きさが違います。